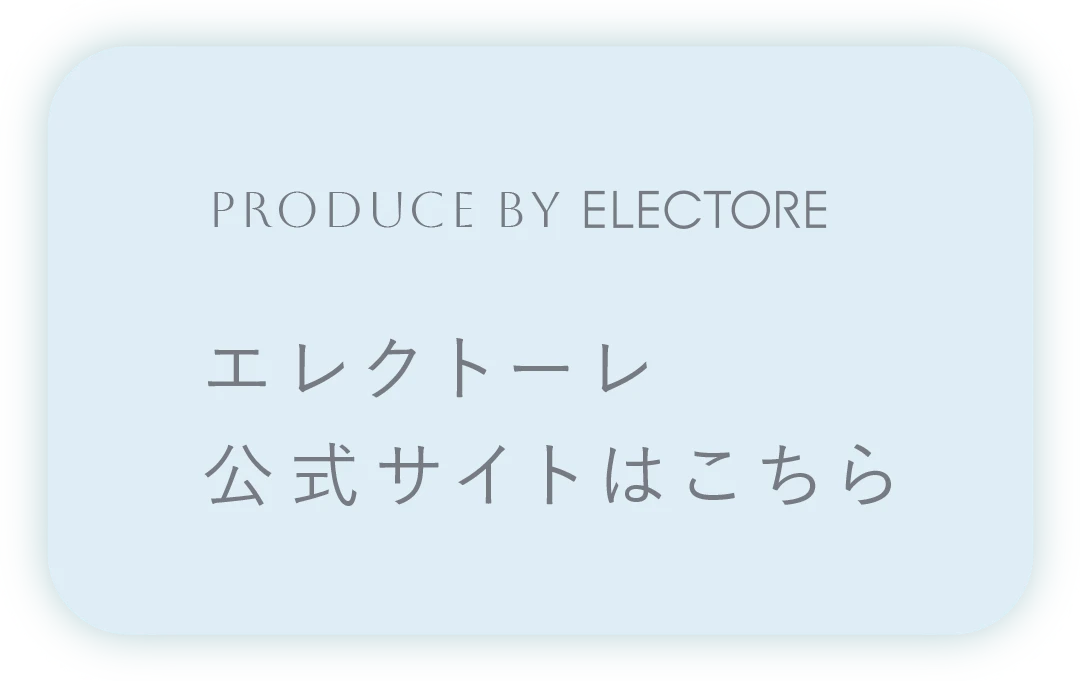美の本質は感動。この考えのもと、深い精神性と伝統美が継承されるさまざまな日本文化を応援しています。
山中漆器 木地師 佐竹泰誌

冨宅:山中漆器の歴史を教えていただけますか。
佐竹:山中漆器の歴史としては350年ほど歴史があります。山中には大聖寺川という川がありまして、そこにお椀が流れてきたそうなんです。それを見て、川の上流に人が住んでいるのではないか、ということで探しに行ったところ、木地を挽く集団が住んでいたそうです。それが山中漆器の始まりと聞いています。
冨宅:山中漆器の特徴はどのようなものでしょうか。
佐竹:山中の特徴としては「縦木取り」ということです。木を輪切りにし、輪を描いて器にします。他の産地は、縦にスライスし、横に寝かせて輪を描く横木取りで、縦木取りの方法で作るのは山中だけでした。今は全国的に山中式が取り入れられているようです。
冨宅:本当に木目が美しいですよね。
佐竹:山中のろくろ技術は産業革命でモーターが出てきたことで、さらに発展しました。山中のろくろは非常に精度が高いです。それまではろくろといっても木の軸で、軸を押さえ、軸に紐を巻いて、奥さんが引っ張って回す。そして旦那さんが回転に合わせて引いていく、というアナログな方法でした。やがて足踏み機になり、一人でできるようになった。そんなふうに発展し、最盛期には200人を超える職人がその技術を切磋琢磨しました。おかげで山中の地はろくろ技術で有名になったのだと思います。
冨宅:木地作りの工程を教えていただけますか。
佐竹:まず原木の乾燥が非常に大切です。約3カ月間かかります。自然乾燥で水分が抜けるまで1カ月、さらに乾燥室に入れて1カ月。木の中の含水率を5%以下まで落とします。そして乾燥室から出し、5%以下だと乾きすぎなので、1カ月ほど大気にさらします。これは一般的な器の場合ですが、作品ですと割れやすい木が多いので、乾燥に約3~5年間かけます。割れないようにゆっくり、ですね。大事なのは乾燥室に入れるタイミングです。 水が抜けていない状態で入れると割れてしまいますので、良い頃合いを見て、乾燥室に入れます。大気にさらす時間も半年くらいかけて仕上げます。木の状態を見ていると「割れたそうな顔をしているな」と、なんとなくわかります。
冨宅:すごいですね。常人にはわからない感度の高さ、感じ取る力ですね。
佐竹:ですから戸をしっかり閉めておいたり、その都度対応していきます。その後、ろくろにかけて形を作り、漆を塗ります。漆塗りは約2~3カ月かかります。漆の綺麗さ、木目の美しさを引き出せるように、20回ほど塗り重ねていきます。全てをこのように積み重ねることで綺麗な作品になっていきますので、木の美しさと漆の美しさを、しっかり引き出せるよう作品を作っていきたいと思っています。
木の持つ空気感を表現し
自然の美を追求する

冨宅:木の状態をよく見るとのこと、まるで木と対話するような感覚は具体的にどのような思いなのでしょうか。
佐竹:木は繊維質です。ですから繊維が入り組んでいる中に刃物を当てるので、樹種によって違います。したがって道具を常に調整します。アジャストしていかないと綺麗な切れ味になりません。そのように木の状態を見ながら道具を合わせていくということです。そして次に、形を作るというよりは、木の持っている空気感を意識しています。形ばかり意識しますと、自然ではなくなるというか。自然の強さ、柔らかさを表現したいと思っています。
冨宅 :無理やり形を作ってしまわず、そのまま生かしてあげるのですね。
佐竹:そうです。私は自然の中で暮らしていますので、あらゆる植物がそこら中にあります。山を散歩していると、葉っぱ一つでもすごく綺麗なんですよね。多分そういうところが僕の中に蓄積されていて、そういうライン、空気感というものを表現したいと思っています。
冨宅:気持ちを込めて、時間をかけて作られるのですね。また、お父様が木地師でいらっしゃって、小さい頃からお仕事を見ていらしていかがでしたか。
佐竹:よく手伝いをしていました。学校から帰ったら、お椀の材料を積む。今日は2千個だ、とか。そういう生活でした。それが別に苦でもなく。そして、父はとても楽しそうに仕事をする人でした。それで、あぁ、そんなに楽しそうなら僕にもできるんじゃないかな、と。それで僕は勤めていた会社を22歳で辞め、この仕事を始めました。しかしなかなか、茨の道でして。
冨宅:実際にお父様と一緒にされてみていかがでしたか。
佐竹:非常に厳しい人でした。いわゆる「ならんものはならん」と。厳しいけど、それだけのことをした人なんじゃないかなと思っています。
冨宅:実際、始めてみると厳しさを感じられて。そんな時は、どのように乗り越えてこられたのですか。
佐竹:技術が足りないとやはりできないことはあります。それでも前に進んでいく、ということでしょうか。だいたい10年間は修行で、耐える、向上し続けるという時間が必要なのだと思います。胆力といいますか、そういったものが必要。決して甘やかしてくれるような父ではありませんでしたから。美について追求していくことが、成長につながると感じました。焼き物でもガラスでも、時代を超えていろんな良いものに触れ、例えば李朝のものがこんな風に綺麗だね、とか。父との会話からモチベーションを得て、前に進むようにしていたのではないかと思います。美術館にもよく行かせてもらいました。その時はわからなくても、自分の中に少しずつとどまっていく。そして時間が経つと、アウトプットできるようになっていき、成長につながっていると思います。
冨宅:本物に触れることは貴重な経験ですね。お父様の教えの中で、大切にされていることはありますか。
佐竹:まず言われたことは、掃除です。掃除を丸くするな、と。掃除というのは隅からしていくんだ、隅への気遣いができないといけないよ、ということだと思っています。今は私自身も弟子がいまして、同じように言います。
大切にしたい「幸せ」を
感じられる美とぬくもり
冨宅:今、伝統工芸の職人さんは継承する方が減少していると思いますが、いかがですか。
佐竹:木地師もすごく減ってきています。最盛期は、山中では200人ほどいましたが、今は30人前後。そんな中、山中には山中漆器産業技術センターという木地師を育てる学校があります。その中から職人となる子が1人でも、技術を継承していただけたらありがたいです。未来にこの技術がつながって、日本の文化として残るとありがたいなと思っています。
冨宅:私も佐竹さんの器を愛用していますが、心を込めて作られた美しい器でいただくと、味も美味しく感じて、とても幸せな気持ちになります。弊社でも、去年の春から無農薬野菜の農業を始めました。環境問題や生態系保全に貢献したいという思いから始めましたが、農業も、従事者の高齢化が進んでおり、若い人に農業を広めたいという思いもあります。農業は楽しくてかっこいいという憧れの職業にしたい。そして同様に、職人さんはかっこいい、というふうに目指す人が増えると、地方の活性化にもつながるのではないかと思っています。時代も変わってきているようにも思います。
佐竹:本当に、そうなってくれたら嬉しいですね。
冨宅:最後に、今後の抱負をお聞かせいただけますか。
佐竹:今後も個展活動をしていき、美しい物を創出して喜んでいただければと思います。
冨宅:5月21日から日本橋三越で個展が開催されるとのこと、楽しみにしております。本日はありがとうございま
した。


木地師 佐竹泰誌
2003年父佐竹康宏氏に師事
2008年日本伝統工芸展初入選
2009年現代美術展入選
2009年石川の伝統工芸展奨励賞受賞
2014年石川の伝統工芸展石川県知事賞受賞
2020年銀座ギャラリー田中にて初個展
現在 日本工芸会正会員(2012年より)
2025年5月21日~27日 日本橋三越本店6階美術部にて個展開催予定