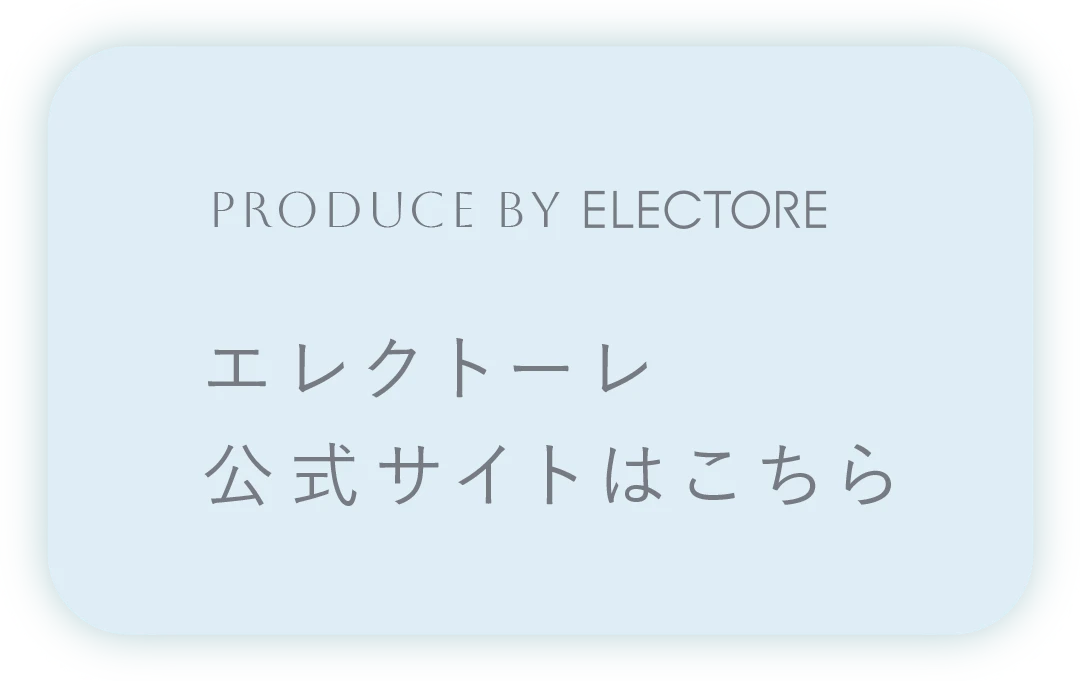美の本質は感動。この考えのもと、深い精神性と伝統美が継承されるさまざまな日本文化を応援しています。
有職彩色絵師 林美木子

冨宅:有職彩色絵師とはどのようなお仕事ですか。
林:有職とは、古くから宮廷に伝わるデザインや儀式のやり方、決まり事に則って描くことです。有職をベースにした彩色、そして絵も描くので有職彩色絵師と名乗っています。
冨宅:昨年のNHKの大河ドラマ「光る君へ」での小道具を手掛けられましたね。
林:檜扇と、鴨の人形ですね。みなさんにとても喜んでいただけたようでよかったです。今までやってきたことが決して独りよがりではなかったんだなと、やってよかったと思いました。
冨宅:平安貴族の装飾品を、現代に生きている人が作り続けているとは、ちょっと不思議な感覚がいたします。
林:そうですね、あまりピンとこない方が多いでしょうね。
まだ駆け出しの職人の頃、貝合わせを作るためのハマグリを探してこい、と言われ、当時の私はハマグリといえば「その手は桑名の焼きハマグリ」しか知らなかったので、桑名へ行けばあるだろうと思って行きました。しかしどこへ行っても無く、日は暮れかかり、一日中歩いてクタクタ。すると暗い店先にお婆さんがいて、「運河の向こうに店があるから行ってごらん」と。これが最後だと思って行ったら、なんと店の前に生簀で生きたハマグリを置いている店があって、もうそれを見たとたん号泣ですよ。
冨宅:まさに導かれたようですね。
林:奥から社長さんが出ていらして、事情を話し、無事に入手できました。その当時はクール便など無く、リュックにいっぱい詰め込んで持って帰ったんですけど、京都駅に着いた時にはもう異臭を放って、とんでもないことになっていました(笑)。
「絵が動いた」という衝撃

冨宅:このお仕事をされるきっかけはどのようなことでしたか。
林:はじめは有職雛人形を作る店の職人でした。人形作りは分業ですので、はじめは彩色だけを担当していましたが、バブル期以降、職人さんが減り、工程のうち一つでも欠けると完成しないので、これやってみない?と言われてやっているうちに、最初から最後まで一人でするようになりました。
冨宅:お父様は桐塑人形作家で人間国宝でいらっしゃいますね。一方、先生は美術大学在学中、ヘビメタのバンドの追っかけをされていらっしゃったとか。
林:そうです。それで父に「出ていけ」と言われて、二十歳で家を追い出されました。こたつだけ持って、大学の友達とアトリエ用に借りていた町屋に住み、昼はギャラリー、夜は芸子さんのお店で働いて生活しました。父は、私が幼少の頃から自作の着物を着せ、将来はお琴の先生にしたかったようなのですが、私は職人になる道を選びました。
冨宅:そうだったのですね。お父様のお言葉で「年齢や性別も超越するような、鶴のようなおじいさんが描いたといってもおかしくない仕事をしろ」ということを印象深く拝見したことがあります。作品を作る上で心がけていらっしゃることはどのようなことですか。
林:職人は年齢、性別、個性がわかる仕事をしてはいけないと。自分の個性をゼロにし、いかに作品を前に出すかという訓練がほとんどです。自分自身、究極のところまで透明にすることで次世代に伝えられるものができる、すべてその人の気持ちが表れると思っています。それが真の職人の仕事だと思っています。
冨宅:仕事もピュアな心でいなければ良い判断はできないと思っています。すべて同じですね。有職のお仕事に特化されたのはいつ頃からですか。
林:渋谷のBunkamuraがこけら落としの年、最初の展示が源氏物語画帖でした。私はそれを観るため、初めて一人で東京へ行きました。鑑賞していると、ふっと絵の中に風が吹き、絵が動いたような気がしたのです。「絵って動くんや!」という衝撃。四~五百年も前に描かれたものなのに、描いた人の“ここを見てほしい”とか“これは良くできた”という気持ちが伝わってくるようでした。良い仕事とは、時間を超えて対話できる、伝わるものなんだ、と感動しました。
冨宅:作家さんの情熱は、時を超えても伝わるものなのでしょうね。私も以前にニューヨークのメトロポリタン美術館でゴッホの「ひまわり」を観た時、ゴッホの情熱やパワーが伝わってきて衝撃を受けた経験があります。今のお話を伺って、本当にそのようなことはあるのだな、と思いました。
林:自分が死んでも作品さえ残っていたら、こうして何百年も先の人と喋れるかも、私もそんな仕事をしたい、と思ったんです。流行とか、売れるとか、そういうことではなく、良いものは本当にずっと良いのだ。言葉で言えば、不変の美というのでしょうが、その時の「絵が動いた」という衝撃は「私もいつかケースの中からお客さんに喋りたい」という決意に変わりました。
冨宅:それが、美を次世代へ伝えるお仕事となっているのですね。
林:本当の美というのは、作るものではないんですよね。ずっとあるもの。あるものを見えているかどうかだけのこと。美は探すものではなく、見えているか否か、ということなのでしょうね。そのような、時を経ても変わらないものを追究していきたいと思っています。しかし、そういうものが時代にそぐわない、時代のスピードに合わないというだけで無くなっていくことが多いので、私はその古いやり方をなんとかキープしていきたい。どうしても時代は前へ前へ、未来へと向かっていくものですけれど、私ひとりくらいそういう人が居てもいいと思うのです。
千年前も今も変わらない
人間の思い
冨宅:先生の作品は華やかさとともに、とても縁起の良さを感じます。
林:医療などがまだ未発達の時代、貴族という特権階級の人たちでさえも避けられないのが、死や病気。それこそ呪術合戦みたいなことを本気でやっていた時代、身を守ることイコール祈りとまじないしかなかったような時代があったのですよね。子供が成長することも難しいような時に、生まれた子供や大切な人を、疫病や不幸からなんとかして守りたいという気持ちが、強い色や模様となって表現されています。
冨宅:色や模様に、そのような意味が込められていたのですね。
林:だから有職の約束事というのは基本的に、すべて祈りの表れ、祈りのバイキングみたいなものなんですよ。魔を払う色、すなわち強い色を使う。例えば、疫病除けは赤で描く、金運は、長寿は…と、いろんな切なる願いを込めて、大切な人の身近に置くことでその人を守ろうとした。まして子供にあげるおもちゃは、親のその祈りが他のものよりずっと強いでしょう。この子を病気から守るためだったら、十個でも二十個でも枕元に置きたいと思いますよね。その思い、大事な人に元気でいてほしいという気持ちは、千年前も今も変わらないのではないでしょうか。
冨宅:本当にそうですね。最後に、今後の抱負をお聞かせいただけますか。
林:今日を頑張ること、今に専念して毎日を過ごしたいです。仕事のない怖さも知っているから、仕事をしてごきげんな毎日だったらいい。おめでたく感じてもらえるような仕事をするためには、私自身がおめでたくないと駄目なので。実際には嫌な時もしんどい時もありますが、それでも大むね「私ごきげんです」と言える状態で仕事することが一番大事。
また、色んな人とお会いして、自分の知らなかった扉が開き、見たことのない景色が見えることが楽しい。今日もこのようにお会いできて楽しいです。技術を磨くだけでなく、毎日が楽しい人生だったらいいなと思います。技術的なことは、辞めずに続けていたら腕は上がりますが、自分のテンションを常にフラットにすることが難しい。苦手な局面でテンパらないで、落ち着けるにはどうしたらいいか、自分と向き合って問い続けています。
冨宅:素晴らしいお話を本当にありがとうございました。


有職彩色絵師 林美木子
86年京都芸術短期大学日本画コース卒業。
父・林駒夫に師事しながら、有職彩色絵師として、平安の古より連綿と続く伝統的な有職の貝桶、貝覆、檜扇をはじめ、有職大和絵による板絵などの作品を制作。以後、個展やグループ展を中心に幅広く活動する。「ブルガリ アウローラ アワード2018」受賞。